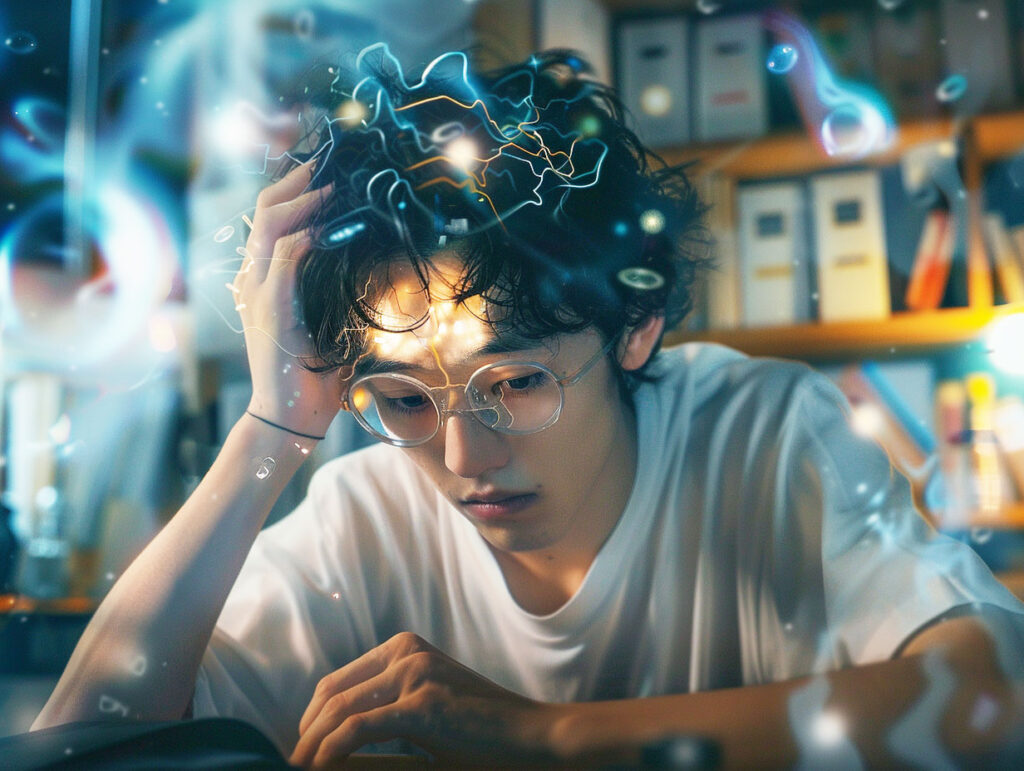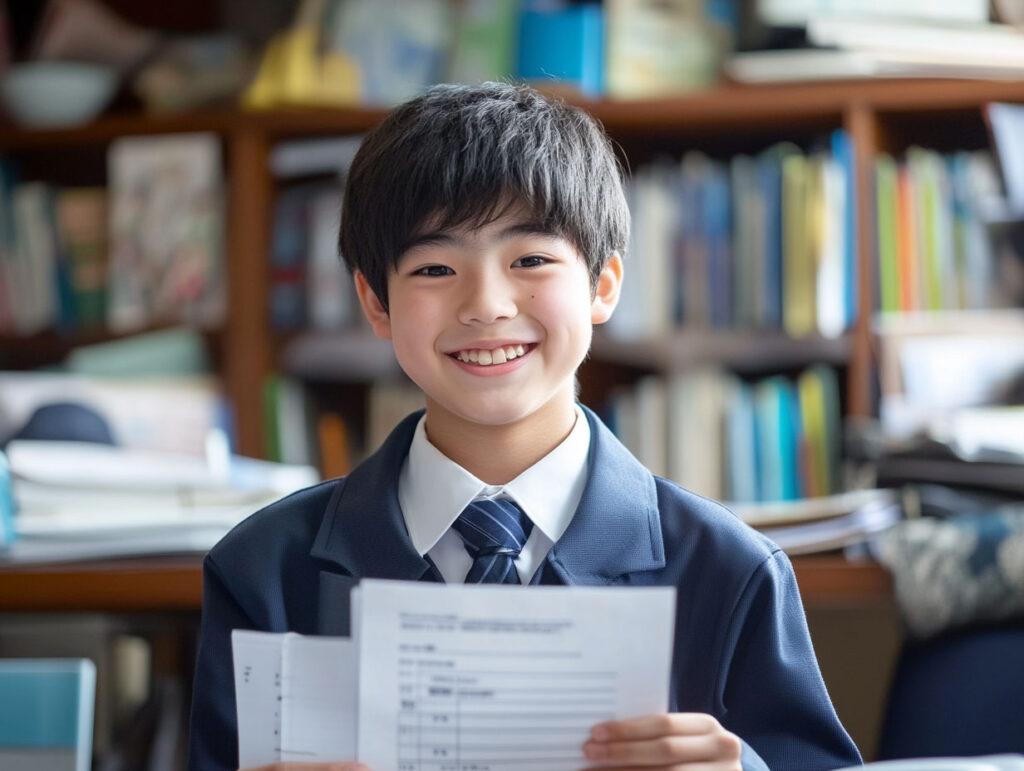
はじめに
こんにちは、Takkiです。一旦期末テストや入試が終わった頃だと思います。テスト終わりでほっとせず、しっかり勉強できていますか?テストの終わりは次のテスト対策への始まりです。勉強がうまくいっている人はもう次の勉強を始めていますよ!
こちらの写真は先月南京に行った際に、訪れた科挙の博物館です。展示を見ながら今も昔も試験に対する熱い思いは変わらないなぁと感じました。この時代における勉強時間や勉強にかける思いを知ると、私が経験した受験はなんと易しかったのか…と思わされます。

さて、この時期になると、特に「勉強たけれども結果が出ない!」というお子様の声を伺います。「頑張ったのに、テストがうまくいかなかった。どうせこれ以上頑張ったって無理だ…」、「自分・子どもには才能がないから仕方ないのかなぁ」と、勉強を諦めるモードに入ってしまっていませんか?今回の記事は、テスト対策を頑張っても上手くいかなかった方が、どうやって次のテストに備えていくべきかについて考える記事となっています。
なぜ毎日をテスト週間化することが必要なのか
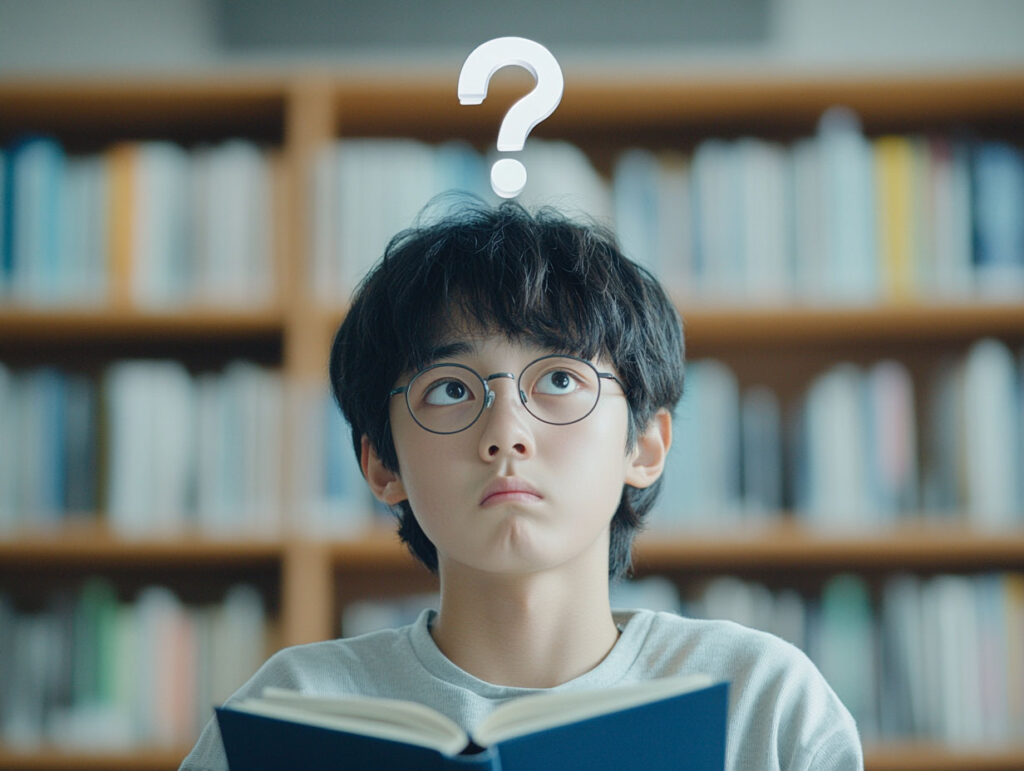
では、まず私から問題提起をさせていただきます。テスト勉強は、本当に必要でしょうか。必要だという声はとても多いでしょう。しかし、私はこのテスト勉強という考え方がそもそも成績が伸び悩む原因であり、「テスト勉強」という言葉は、テストの前以外は勉強をしなくていい」という都合のいい言い訳として使われているのではないかと考えています。
このような考え方のもとでは、生徒さんはテストが近づかない限り勉強をしなくてもいいことになってしまいます。そんな訳がありませんよね。一つのテストの終わりは次のテストの始まりです。つまり、受験まで残された毎日は、全てテスト週間だと考える必要があります。
このことを意識して勉強を進めているライバルが現実に存在しています。そのような生徒さんは、確実に毎日メキメキと力をつけて最後まで成長し続けます。こんなに頑張っているライバルに対して、テストの前しか勉強していない生徒さんが勝てる訳がありません。
テストの結果を見て「勉強したのに…」と思う方もいると思いますが、この「勉強した」という感覚のハードルがあまりにも低い可能性が高いです。あなたにとっての「勉強した」は、ライバルにとっての、「あまり勉強が捗らなかった…」、「サボってしまって全然対策ができていなかった…大失敗だ…」かもしれません。ですから「勉強したのに」と嘆く前にまず、自分、お子様は「本当に勉強したのか?」と問い直すことから始めてください。
関連記事:どう見る?テストの点数-平均点の罠に騙されるな!-
毎日テスト週間化のすすめ
ここからは、毎日をテスト週間化する上で意識すべきことをまとめます。それは、①勉強しない日をなくす、②目的意識を持った勉強、③長期的な目的意識を持った勉強の3点です。
①勉強しない日をなくす

先述の内容と重なりますが、そもそもテストの終わりはテストの始まりです。ですから、宿題しかやらない日を作るのはもってのほか。(宿題もやっていないなんていうことはありませんよね?)宿題は生徒みんながやるものなので、やったところでライバルにリードを取ることはできません。むしろそれだけをやっていたら、宿題プラスアルファの学習をしているライバルにリードを許す一方です。
では、どんな勉強をしたら良いのでしょうか。それについては②をご覧ください。
関連記事:勉強しないのは性格のせいじゃない!? 9割の親が気づいていない“やる気を奪う習慣”
②目的意識を持った勉強
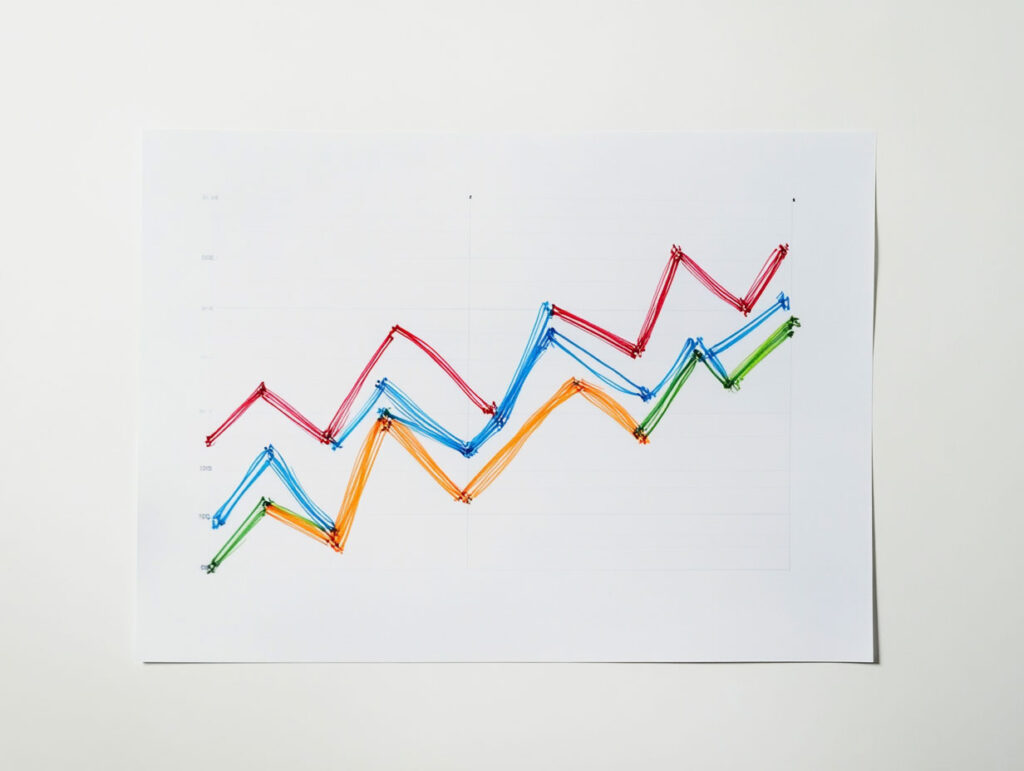
この宿題プラスアルファの学習として何をすべきか考えましょう。当然次にテストにつながる勉強をしたいですね。そこで、テスト範囲発表前にテスト範囲を予想します。
学校の先生も計画的に授業をしています。ですから毎回のテスト範囲を踏まえてテスト範囲を予想することは可能です。予想したテスト範囲に合わせて予習が得意なら予習を、復習が得意なら復習をすると良いですね。
ダラダラとなんとなく勉強するのをやめて、自分が予想したテスト範囲に向けた勉強をすると効率が良くなります。これを自分で全て決めて学習するのは難しいかもしれません。その場合は家庭教師に相談したり、親御さんと自分が決めた目標を共有し相談するなど、周りの大人にうまく頼りながら学習するとやりやすいと思います。
関連記事:【勉強法】効果的な復習の方法とは?学習内容を忘れないために!
③長期的な目的意識を持った勉強

自分がどこの高校、大学に行くのかを決定せずに努力するのは難しいです。自分のライバルは誰なのか、誰に勝つ必要があるのか、どのくらいの点数が必要なのか…それは志望校によって変わってきます。ですから自分が将来何をやりたいのか、そのためにどこの学校に行くべきかを見据えた学習が必要です。特にこの部分はインターネットの情報、オープンキャンパスに行くことによって少しずつ見えてくる部分かと思います。
特にこの部分は親御さんのサポートが必要になってくる部分です。特に中学生のお子様はオープンキャンパスの情報を調べるのが難しかったり、会場へのアクセスが難しいことが予想されます。ですので親御さんが「オープンキャンパスに行こうよ」と誘ってあげるような声掛けをすることでお子様は一歩踏み出せることが予想されます。オープンキャンパスに行くことを押し付けるのではなく、一緒に行こう、一緒に情報を調べようと誘ってあげるようなスタンスが重要です。
関連記事:なぜ勉強するの?集中できないときは学ぶ意味と目的を明確にしよう!
おわりに

いかがでしたか。私の経験談になりますが、夢を持っているお子様の勉強に対するモチベーションや、辛い時の踏ん張りは目を見張るものがあります。担当した生徒さんの中には、「〇高校で学んで絶対に調理師になりたい!」「国際的に活躍するメイクアップアーティストになるために英語を頑張るぞ!」「〇大学で勉強して、ロボットで介護現場を助けたい!」というように、何かを将来成し遂げたいから学びたい!そのために日々の勉強や受験を頑張りたい!と語ってくれる生徒さんがいました。そのような生徒さんは前向きに粘り強く勉強に取り組んでくれました。
しかしこのように具体的な夢を見つけるのは難しいことだと思います。まずは、行きたい高校、大学を始めるところからで構いません。ぜひ、ご家庭と家庭教師が協力して、お子様が夢を持って勉強に取り組めるようにサポートしていきましょう!