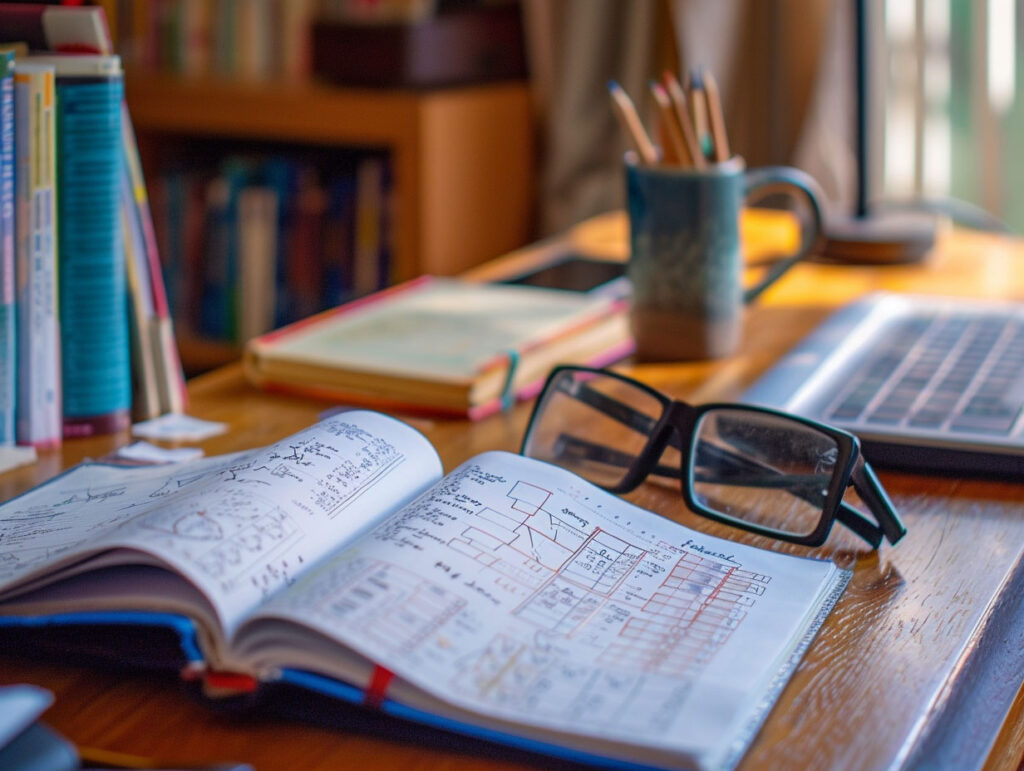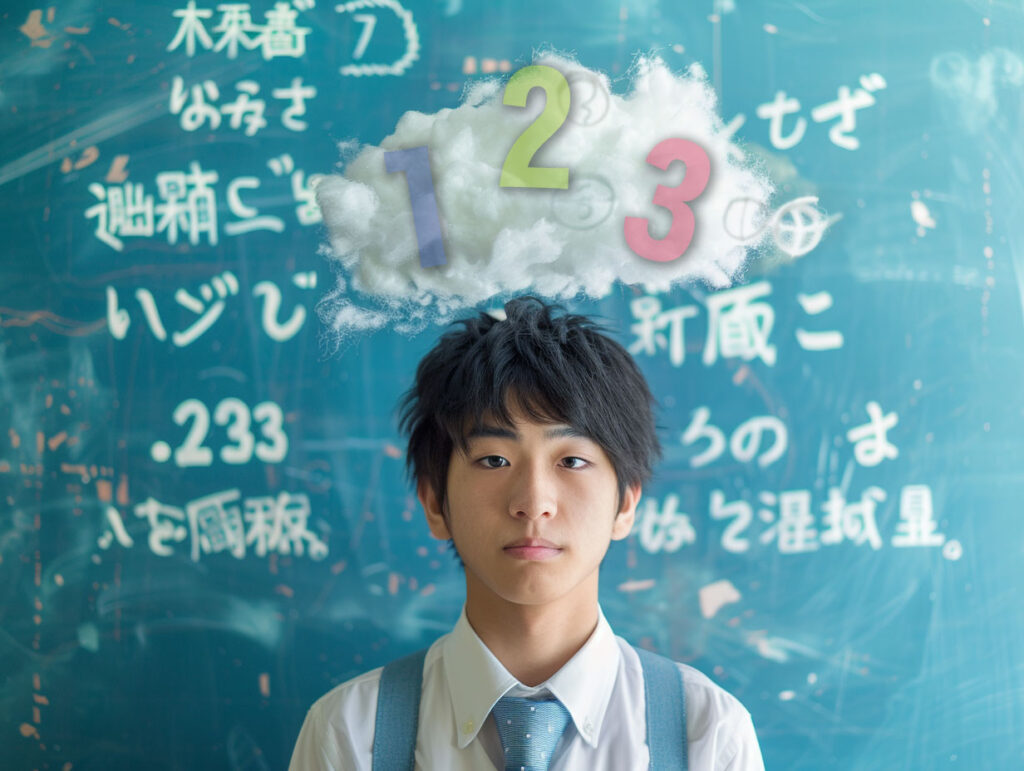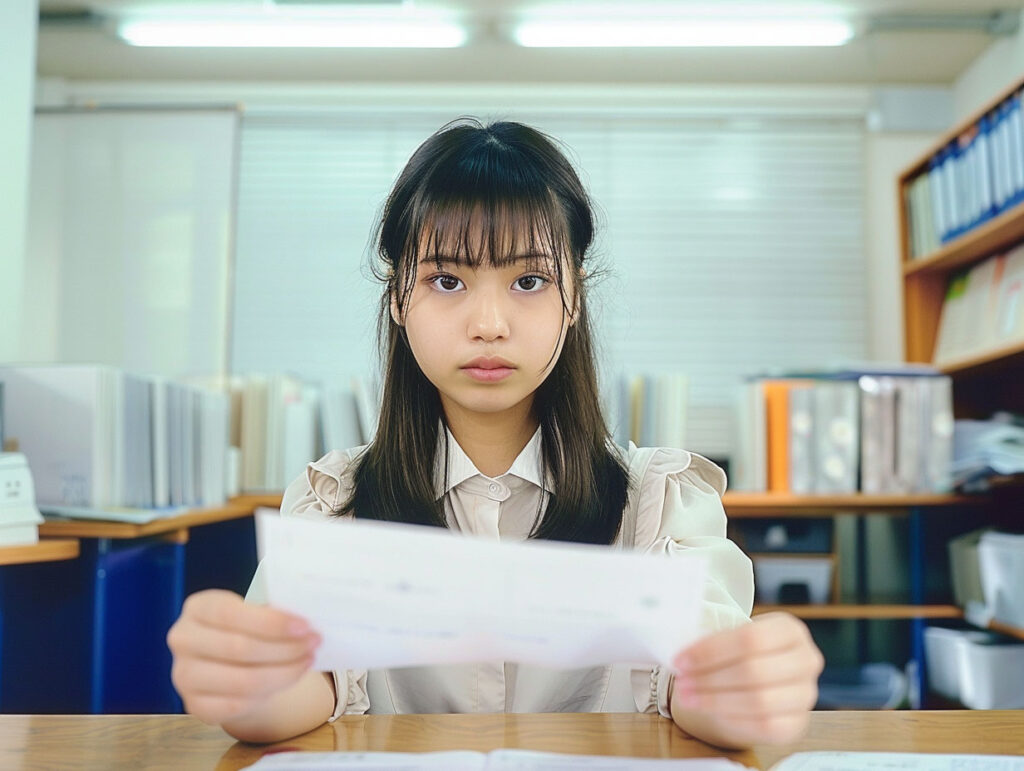中2の春休み、どう過ごす?
中2のお子さんの保護者にとって、春休みは、中学もあと1年と思うと、時の早さに驚かれるのではないでしょうか。
お子さんが中学生活を順調に過ごし、塾通いも習慣になり、ほっとしていたのも束の間、いよいよ高校受験のことを真剣に考え始めなければならない焦りも感じるかもしれません。
改めてこれまでの通知表を見て、5段階の3~4くらいの中程度であれば、特に授業でつまずいた様子もなく、見守るだけでよかったのが、いざ受験を意識しだすと、春休みの過ごし方や自宅学習の時間など、これまでの延長でよいのか、さまざまな疑問が頭をよぎるかと思います。
そこで今回は、受験を見据えて、中2の春休みの勉強時間を最大限に活かす学習法をご紹介したいと思います。
結論
- 春休みは実質10日ほどしかないので優先順位を決めて学習する。
- 復習に絞り、数学と英語を中心に、苦手な単元の克服を重視する。
- 得意なところは時間を決めてテンポよく、苦手な単元はじっくり取り組む。
- 苦手な単元は、同じ問題を2回以上繰り返し学習する。
- 学校や塾の宿題がある場合は、宿題と関連する単元を勉強することで効率を上げる。
- 学習計画の実行には、伴奏するペースメーカーが不可欠で、つまずき箇所を見極め、わかるまで解説できる学習サポーター(家庭教師)が必要。
- 勉強の仕方がわかることで、自宅学習も習慣化していく。
春休みは短い

春休みは長くありません。3月下旬〜4月上旬の概ね12〜14日間程度です。実質10日ほどと考えてよいと思います。
理想は、春休みの間に1年間の総復習、苦手科目の克服、進級に備えた予習、これらを通して受験に向けて自宅学習の時間を伸ばすなど、いろいろとありますが、これではやるべきことが多すぎます。
学校によっては宿題もあります。塾に通っている場合は塾の勉強もあるでしょう。時間が限られた中で、こうしたやらなければならないことが盛りだくさんあるため、優先順位をきちんと決めて進めていく必要があります。
関連記事:春休み、ただ遊ばせるだけで大丈夫?新学期に差がつく家庭と後悔する家庭の決定的な違い
優先順位の決め方
復習に注力

予習は、新学年の授業にスムーズに入っていけるため無駄ではありません。また、一部の塾では、学校の授業の先をいくことで、授業での理解度を上げ成績に結びつけていくことも行われていますが、自宅学習の習慣がある優秀な生徒さん以外は、苦手科目がそのままになってしまいがちです。
お子さんが中程度の成績で、自宅学習の習慣が十分に定着していない場合や、自宅学習の時間が短い(2時間以内)場合は、復習に注力しましょう。また、塾で伸び悩む場合も復習が優先です。
関連記事:間違えた問題をそのままにしない!復習の徹底が成績アップの近道
数学と英語を優先
基本は、数学と英語を中心に勉強の計画を立てます。
暗記系の科目の社会・理科は、各単元の独立性が比較的高いこともあり、つまずきがあっても影響は限定的で、短期間での追い込みが可能ですが、数学と英語は、苦手な単元があったり、つまずきをそのままにしておくと先に進めません。
春休みの機会に、数学と英語の苦手な単元を克服しましょう。最低限、数学なら計算問題、英語であれば単語と熟語だけでも、しっかり身につけ、ケアレスミスをできるだけ無くしておきたいところです。
苦手な単元をお子さん自身が把握している場合はよいのですが、何がわからないかがわからない様子の場合は、うまく聞き出すか、定期テスト・教科書ワーク・ノート・塾の問題集などを手がかりに把握しなければなりません。学校の面談を活用したり、塾に聞いてみる手もありますが、いずれにせよ、学習計画を立てる前にサポートが必要になります。
関連記事:忙しい中学生の味方!短時間で成果を出す“勉強の質”を高める方法
学習計画の立て方
時間を決めるか、範囲を決めるか

時間を決めて勉強するのが合っている生徒さんと、時間ではなく単元(範囲)を決めて勉強する方が合っている生徒さんがいます。
どちらがお子さんに合っているかは、お子さんの状況と学習内容によって異なるため見極めが必要です。
一般的には、勉強の習慣化が身についていない生徒さんの場合は時間ベース、基礎がある程度できていて、モチベーションの高い生徒さんの場合は単元ベースと言われています。
私は一律にどちらかに決めてしまうのではなく、使い分けるのがよいと考えています。例えば、得意な教科や単元は、時間を決めてテンポよく進め、苦手なところは、単元ごとにじっくり取り組むことをお薦めしています。
春休みは、中程度の成績であれば、得意な教科・単元で時間を使うより、苦手な単元を克服することを意識した時間割がよいように思います。時間ベースだけになると、理解度に関係なく時間が来たら終わりになるため、成績が頭打ちになり、伸びない原因にもなってしまいます。
関連記事:長期休暇を活用!苦手科目克服のための効果的な学習計画の立て方
学校の宿題がある場合
春休みに1年の総復習の宿題が課されることがあります。そして、新学年の最初には、宿題をもとに、習熟度を確認するテストもあります。
こういう場合は、学校の宿題が優先です。高校受験に影響する内申書・内申点は、中学校が作成しますので、学校の教育方針を遵守するのが基本です。
そして、学校、あるいは塾の宿題がある場合の学習は「宿題と関連する単元」を学習しましょう。こうすることで、宿題と自主学習の相乗効果で、より効果的な学力向上が図れます。
2回以上繰り返す
苦手単元は、基礎を2回以上、繰り返し学習するように計画を立てましょう。できれば3回です。繰り返すことで、基礎が固まり学力が定着していきます。
わからないところでも、わからないなりに繰り返し基本問題に取り組んでいると、頭の中に少しずつ内容が残っていきます。この積み重ねがとても大切です。この感覚を養うことで、自宅学習のコツが徐々につかめていけます。
関連記事:「成功体験」でやる気を引き出す!中学生の勉強習慣が身に付くヒント
朝型でなければいけないか

理想は朝型です。頭がすっきりしている午前中の早い時間から机に向かうことができるとよいのですが、朝が弱い生徒さんも多いのも現実です。また、起きれない日があった時に、気持ちが切れてしまい学習習慣まで崩れてしまうかも知れません。
一方、夜型は生活リズムが乱れがちになるデメリットはあるものの、寝る前に記憶を定着しやすいという特徴があります。
午前中はすっきりとした頭で主に数学と英語、夜は暗記系の科目という感じで、両方のいいとこ取りで、一日をうまく使えばよいのではないでしょうか。
春休みの学習計画の一例
以上をまとめて、成績が中程度・学校/塾の宿題ありの場合の学習計画の一例を作ってみました。一日の勉強時間は、トータルで5時間程度です。
<3日で1クール>
・学校の宿題(50分) 午前 or 午後
・塾の宿題(50分) 午前 or 午後
・数学(宿題と関連する単元) 午前
・英語(宿題と関連する単元) 午前
・1日目は国語/2日目は社会/3日目は理科(50分) 午後
*このサイクルを3〜4回繰り返す。
* 宿題が一通り終わったら、苦手単元に注力する。
* 宿題がない場合は、最初から苦手な単元を中心に学習する。
学習計画の実行に欠かせないこと
ペースメーカー
ほとんどの学校で、夏冬春の長期休みに入る前に、生徒さんに一日の過ごし方のスケジュールを立てさせます。しかし、この通りに完遂できたことは、なかなか無いのではと思います。
つまり、自宅学習の習慣が身についていない場合は、学習計画を作っただけで終わってしまう可能性もなきにしもあらずです。学習計画を立て、お子さんと伴走してくれる「ペースメーカー」の存在が不可欠になります。
解答の解説
自力で苦手単元を克服しようとする場合、大きな壁に当たります。苦手なところは、そもそも問題集の解答の解説自体を理解できないこともあるからです。これではいくら時間を割いても、わからないところがわからないままです。お子さんの視点で、苦手な問題の解答を「なるほど!」と納得するまで掘り下げて解説してくれる人が必要です。
また、ありがちなのが、得手不得手と好き嫌いの混同です。好きな教科でも苦手な単元があり、逆に、嫌いな教科でも得意な単元があるように、苦手な単元とつまずき箇所の見極めは、生徒さん自身でも難しい時があります。客観的に判断するサポートが必要になってきます。
家庭教師の検討

自宅学習における「学習計画のペースメーカー」「わかるまで解説」「注力単元の分析」の課題に取り組むことが得意な勉強サポーターがいます。家庭教師です。
本記事で学習スケジュールの例をご紹介しましたが、実績のある家庭教師協会に所属している講師であれば、お子さん一人ひとりの状況・性格・目標などにマッチしたオーダーメイドの学習計画(カリキュラム)を提案できますので、より充実した春休みを過ごすことができます。
関連記事:個別指導塾・家庭教師を「使って」成績アップ! 〜個別指導の有効な使い方〜
まとめ
春休みは、春の訪れを感じながら新学年に向けて気持ちが動くため、気も緩んでしまいます。長いようで短い春休みに、中2の復習を怠らないことが、中3から本格化する受験勉強への最大の備えになります。特に、追い込みが効きにくい、数学と英語の苦手単元を克服し、基礎固めに注力しましょう。わからないところを納得いくまで解説してくれる家庭教師は、学習サポーターとして最適です。勉強方法がわかることで、自宅学習の習慣も身につき、新学年も不安なくスタートさせることができます






 英単語が苦手な高校生必見!どんどん覚えられる10分英単語勉強法
英単語が苦手な高校生必見!どんどん覚えられる10分英単語勉強法